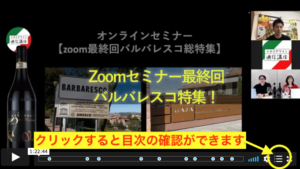【見逃し配信】講義vol.10(20220318) 約83分
※画面の右下をクリックすると、目次の確認、頭出しができます。
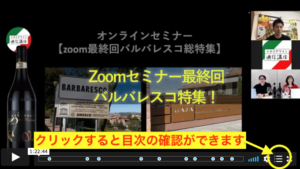
●質問1(59:40):チェダーチーズに合うイタリアワイン
酸味やクセの少ないチーズはトロピカルな白ワインがおすすめ!
・デッペール|ヴェルメンティーノ・ディ・ガッルーラ “ルーリス” 2019
・【新ヴィンテージ】リッキ|ガルダ シャルドネ “メリディアーノ” 2019
・ラティウム|ソアヴェ “カンポ・レ・カッレ” 2019
●質問5(01:18:15):ビターチョコレート、ミルクチョコレートにそれぞれ合うイタリアワインの品種があれば教えてください。
チョコレートと相性のよい甘口ワインやリキュールはこちら
・エービーセレツィオーネ|リクオーレ・アル・カカオ “アナンダ” (700ml)
・レ・チマーテ|モンテファルコ・サグランティーノ パッシート 2011 (375ml)
過去のアーカイブはこちら
【見逃し配信】講義vol.9(20220304) 約62分
※次回第12回の最終回は、「zoomオンラインセミナー」を3/18(金)に開催予定でございます。改めて詳細をご連絡いたしますので、お楽しみに。
【見逃し配信】スペシャルセミナー|人気講師紫貴あきさん&トップソムリエ若原美紀さんによる特別セミナー!(20220206) 約59分
★紫貴あきさんのプロフィールはこちら
https://www.adv.gr.jp/teachers/detail/82
★若原美紀さんのプロフィールはこちら
https://www.adv.gr.jp/teachers/detail/365
【見逃し配信】講義vol.8(20220113) 約39分
※次回第11回、12回は、「zoomオンラインセミナー」を開催予定でございます。改めて詳細をご連絡いたしますので、お楽しみに。
【見逃し配信】講義vol.7(20211119) 約52分
【見逃し配信】紫貴あき先生による特別セミナー『学べばもっと楽しい!イタリアワイン通信講座』(20211029) 約46分
紫貴あき先生のプロフィールはこちら
https://www.adv.gr.jp/teachers/detail/82
【見逃し配信】講義Vol.06(20211015) 約40分
【見逃し配信】講義Vol.05(20210917) 約1時間
【見逃し配信】講義Vol.04(20210811) 約1時間
【見逃し配信】講義Vol.03(20210720) 約1時間
【見逃し配信】プチ講義Vol.02(20210604) 約10分
【見逃し配信】プチ講義Vol.01(20210428) 約20分